はじめてVODサービスを契約したのはいいけど、ハズレ映画ばかり引いちゃって疲れてません?「2時間返せよ…」って思った経験、私だって何度もあります。
今回は映画好きの私が観る「ハズレ映画」回避テクニックをたっぷりとシェアしたいと思います。
この記事を読むことで以下のことが分かりますよ!
- 映画選びで失敗しない秘訣5つ
- 意外と多い!ハズレ映画を引きやすい典型的な選び方
- ハズレ映画でも得られる意外な学び
もう二度と「この時間返して!」と叫ばなくて済むよう、私の経験から導き出した知恵をぜひ活用してみてください。
私がハズレ映画を引かないためにやってる5つのこと
皆さんは映画を選ぶとき、どんな基準で選んでいますか?タイトルやサムネイル、好きな俳優が出ているからという理由だけで選んでしまうと、期待はずれに終わることも少なくありません。
私も長年の映画鑑賞の中で、数え切れないほどの「ハズレ映画」に出会ってきました。しかし、その経験から学んだことで、今では確率高く「当たり映画」を見つけられるようになりました。
以下は私が普段から実践している、ハズレ映画を避けるための5つのテクニックです。
- 映画祭や批評家の評価をチェック
- 表に出ない「裏方」情報を重視
- 配給会社の特色を把握
- サービス内の特集やキュレーションを活用
- 映画SNSのマニアをフォロー
これらのポイントをひとつずつ詳しく見ていきましょう。
映画祭や批評家の評価をチェック
映画選びで最も確実なのは、すでに評価が固まっている作品を選ぶことです。
私はカンヌやベネチア、サンダンス、トロントといった主要映画祭の受賞作や話題作をメモしておき、一般公開されたらチェックするようにしています。
「えっ、そんな情報どこで得るの?」と思うかもしれませんが、映画専門サイトやSNSで映画祭の時期になるとまとめ記事が出るので、それを保存しておくだけでOK。
特に日本アカデミー賞や米国アカデミー賞(オスカー)などの主要な映画賞にノミネートされた作品は、一定のクオリティが保証されていると考えて良いでしょう。
もちろん、賞を取った作品が必ずしも自分の好みと一致するわけではありませんが、少なくとも「明らかな駄作」を避けるフィルターとしては非常に有効です。
表に出ない「裏方」情報を重視
多くの人は監督や主演俳優だけで映画を選びがちですが、実は「裏方」のスタッフ情報こそ、その映画の質を左右する重要な要素なんです。
例えば、脚本家、撮影監督、編集者、音楽担当者など、表舞台には立たないけれど作品の質を大きく左右する人たちの名前をチェックするようにしています。
「この脚本家の作品は展開が読めない」「あの撮影監督の映像美には惚れ惚れする」「この編集者の作品はテンポが良い」など、裏方スタッフに注目することで、より深いレベルで映画を選べるようになりました。
私の場合、特に音楽担当者には注目していて、ハンス・ジマーや久石譲、坂本龍一といった作曲家が関わっている作品は、音楽だけでも価値があると判断しています。
裏方情報は映画のエンドロールや公式サイト、IMDbなどの映画データベースで簡単に調べられますよ。
配給会社の特色を把握
意外と見落としがちなのが、その映画を配給している会社の特徴です。
配給会社には、それぞれ得意分野や審美眼があります。例えばA24やNEON、日本ならばギャガやビターズ・エンドなどのインディーズ系の配給会社は、商業性だけでなく芸術性や独創性を重視した作品を扱うことが多いです。
「この配給会社の作品は外れが少ない」という経験則を積み重ねることで、未見の映画でも当たりを引く確率が上がります。
逆に、大手配給会社の中には商業的な成功を狙って「量産型」の作品を多く出しているところもあるので、そういった会社の作品は特に評判を確認してから選ぶようにしています。
配給会社のラインナップやこだわりを知ることは、映画選びの精度を高める上で非常に効果的な戦略なんですよ。
サービス内の特集やキュレーションを活用
NetflixやHulu、Amazon Prime Videoなどの配信サービスには、編集部が選んだ特集企画やキュレーションがあります。
「アカデミー賞受賞作品特集」「映画祭で話題になった作品」「この監督の全作品」など、テーマ別にまとめられているコレクションは、一定の品質が担保されていることが多いです。
私がよく利用するのは、「批評家絶賛」や「カルト的人気作」といったカテゴリ。これらは一般的な人気とは別に、映画に詳しい人たちが推している作品が集められていることが多く、マニアックながらも質の高い体験ができます。
また、シーズンごとに更新される特集も見逃せません。年末年始や夏休みなど、各サービスが力を入れて選りすぐった作品を紹介することが多いので、その時期にチェックするのもおすすめです。
映画SNSのマニアをフォロー
最後に私が最も重視しているのが、映画SNSでの情報収集です。
特にFilmarksなどの映画特化型SNSでは、自分と映画の好みが近いユーザーを見つけてフォローしておくと、その人のレビューやリストが自分の映画選びの参考になります。
私も数年前から映画の趣味が似ている数人のユーザーをフォローし続けていますが、その人たちが高評価をつけた作品は、私も楽しめることが多いです。
特に自分が好きな映画に深い考察や的確なレビューをしている人を見つけたら、その人のアカウントをチェックしてみてください。他にどんな作品を高評価しているかを見れば、新たな発見があるはずです。
映画の趣味は千差万別。評論家の意見より、同じ感性を持った一般の映画ファンの意見の方が参考になることが多いですよ。
ハズレ映画を引きやすい選び方(私の失敗談から)
映画選びで失敗する瞬間って、実はパターンがあるんです。特にVOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスが普及した今、その手軽さゆえに陥りやすい罠があります。
私自身、数えきれないほどの「時間を無駄にした…」と感じる映画選びをしてきました。その経験から、ハズレ映画を引きやすい典型的なパターンをお伝えします。
皆さんは心当たりがありませんか?
- サムネイルの見た目だけで選んでしまう
- VODのランキングを鵜呑みにする
- 評価やレビューをろくに見ない
- 見放題だからという理由だけで選ぶ
- 好きな俳優だけを基準にする
それぞれの失敗パターンについて、私の痛い経験とともに詳しく解説します。
サムネイルの見た目だけで選んでしまう
これは私がかつてよくやっていた失敗です。VODサービスを流し見していると、目を引くサムネイルの作品に思わず手が伸びてしまいますよね。
ある日、とあるSFスリラー映画のサムネイルに惹かれて再生したところ、実際の内容はB級感満載の低予算映画で、設定も展開も支離滅裂。2時間を無駄にしてしまいました。
サムネイルは基本的にマーケティング戦略の一環です。特に直近の作品は、クリック率を上げるためにインパクトのある画像を選んでいることが多いです。
画像のインパクトと作品の質には相関関係がないことを肝に銘じておくべきでしょう。気になる作品を見つけたら、必ずあらすじや制作年、スタッフ情報などを確認する習慣をつけることが大切です。
私は今では「このサムネイル、なんかすごく刺激的だな…」と思ったら逆に警戒するようになりました。中身で勝負できる作品は、必ずしもセンセーショナルなサムネイルに頼らないことが多いからです。
VODのランキングを鵜呑みにする
「今週のトップ10」「急上昇中の作品」など、VODサービス内のランキングを信じて選んだ結果、期待外れだった経験は数知れません。
特に悲しかったのは、あるサービスで「視聴者満足度96%!」と表示されていたコメディ映画を選んだときのこと。実際に観てみると、B級どころかC級の粗製乱造作品で、「いったい誰がこれに満足したんだ?」と画面に向かって叫んでしまいました。
各サービスのランキングやおすすめは、必ずしも質を反映したものではなく、単に「多くの人が視聴した」という指標にすぎません。また、サービス内の評価は母数が少なかったり、配信初期は作り手側の関係者による評価が多かったりすることもあります。
さらに、アルゴリズムによる「あなたへのおすすめ」も完璧ではありません。私の場合、一度観たホラー映画のせいで、次々とホラー作品をおすすめされた時期がありましたが、実は私はホラーがあまり得意ではないのです。
VOD内の指標はあくまで参考程度に留め、外部の信頼できるレビューサイトでの評価も併せてチェックするのがベストです。
評価やレビューをろくに見ない
「とりあえず観てみよう」という軽い気持ちで、評価やレビューを確認せずに再生ボタンを押してしまった結果、悲惨な映画体験をしたことが何度もあります。
特に痛恨だったのは、大好きな俳優が出演する新作を即座に観たときのこと。後で調べたら、その作品はRotten Tomatoesでわずか12%という壊滅的な評価を受けていたのです。事前に知っていれば避けられたのに…と後悔しました。
映画は2時間前後の時間を要する娯楽です。たかが2時間と思うかもしれませんが、年間で考えると貴重な時間。その時間を充実させるためにも、少しだけ事前調査をする価値はあります。
私は今では必ずFilmarksやRotten Tomatoesなど複数のレビューサイトをチェックするようにしています。特に批評家とユーザー両方の評価を確認することで、より正確な判断ができるようになりました。
ただし、評価が低くても自分の趣向にぴったり合う作品もあるので、絶対視しすぎるのも考えものですが。
見放題だからという理由だけで選ぶ
「せっかく契約しているから、追加料金のかからない見放題作品から選ぼう」という心理は非常に分かります。私もそれで何度も失敗してきました。
ある月の「見放題に新しく追加された作品」の中から、あまり興味のないジャンルの映画を選んで観たことがあります。結果は予想通り。「なぜこれを最後まで観てしまったのか…」と自問自答する羽目になりました。
VODサービスの見放題枠には、新作や話題作よりも比較的古い作品や、あまりヒットしなかった作品が多く含まれていることがあります。もちろん、埋もれた名作も存在しますが、「見放題だから」という理由だけで選ぶと、当たりを引く確率は下がりがちです。
私の経験則では、本当に観たい作品であれば、追加料金を払ってでも観る価値があります。「時間」という最も貴重なリソースを考えると、追加300円程度の出費は惜しむべきではないでしょう。
今では「見放題枠内で何か観よう」ではなく、「本当に観たい作品を探そう」という姿勢に変えています。
好きな俳優だけを基準にする
これは私が長年抱えてきた弱点です。好きな俳優が出演しているというだけで、作品の全体的な質を考慮せずに選んでしまうのです。
特に悲しかったのは、尊敬する名優の晩年の作品を片っ端から観ていたときのこと。残念ながら、キャリア後半には明らかに出演作の質が落ちていて、その俳優の演技だけが光る「一人だけ別の映画に出ているような作品」が多かったのです。
俳優にも当たり外れがあります。どんな名優でも、すべての作品が傑作とは限りません。特に人気絶頂期の俳優は、多くのオファーから選び切れずに質の低い作品に出演してしまうこともあります。
今では好きな俳優の出演作を選ぶ際も、その作品自体の評判や、監督・脚本家などの情報もしっかりチェックするようにしています。
一人の演者だけでは映画は成立しません。総合的に見て選ぶことが、良質な映画体験への近道です。
観て後悔した映画でも何かしら学べる!(とポジティブに考えよう)
映画を観終わって「あぁ…時間返して…」と思うことは誰にでもあります。でも、そんなハズレ映画との出会いも、実は無駄ではないんです。
私自身、数多くの期待外れ映画を観てきましたが、振り返ってみるとそれらの経験から得たものも少なくありません。
ハズレ映画を観てしまった後、どうポジティブに捉えられるか、その視点をご紹介します。
- 映画選びの「ハズレ回避能力」が向上する
- 評価眼が養われる
- 意外な会話のネタになる
- 良作の価値を再認識できる
- 部分的な良さを見つける訓練になる
それでは、一つひとつ掘り下げていきましょう。
映画選びの「ハズレ回避能力」が向上する
ハズレ映画を引いた経験は、今後の映画選びに生かせる貴重なデータになります。
私はかつて、某人気シリーズの続編を何の疑いもなく観て大失敗した経験があります。その後、「なぜつまらなかったのか」を分析した結果、オリジナルの監督や脚本家が関わっていない続編は注意が必要だということを学びました。
また、特定の監督の作風が自分に合わないことや、ある俳優の演技スタイルが苦手だということも、ハズレ映画を通じて気づくことができます。
つまり、ハズレ映画は「自分の好みの輪郭」をはっきりさせてくれるんです。自分がどんな要素(テンポ、ストーリー展開、演出スタイルなど)に価値を置いているのかが明確になり、結果的に映画選びの精度が上がっていきます。
「この失敗は未来の自分への投資だ」と思えば、少し気が楽になりませんか?
評価眼が養われる
ハズレ映画を観ることで、「なぜこの映画はダメなのか」という分析力が身につきます。
例えば、物語の設定は面白いのに展開がおかしい、キャラクターの行動に一貫性がない、伏線の回収が不自然、演出がくどい…など、作品の弱点を具体的に言語化する能力が養われるのです。
私も以前は「なんかつまらなかった」としか言えなかったのが、今では「前半と後半でトーンが一致していない」「キャラクターの動機付けが弱い」など、より具体的に問題点を指摘できるようになりました。
この分析力は、逆に良い映画を観たときにその価値をより深く理解することにもつながります。「この映画がなぜ素晴らしいのか」を言語化する能力も同時に向上するからです。
批評眼を養うことは、単に映画をより深く楽しむためだけでなく、物語や表現に関する普遍的な理解を深めることにもなります。その意味で、ハズレ映画も立派な「教材」と言えるでしょう。
意外な会話のネタになる
驚くべきことに、あまりにもひどい映画の方が、話のネタとしては優秀だったりします!
「あの映画、どうだった?」「いやぁ、とんでもなくひどかったよ!」という会話から盛り上がることって、意外と多いんです。特に映画好きな友人との間では、「あの駄作を知っているか」というのは一種の通貨のように機能します。
私も友人たちと「人生で観た最低の映画」というテーマで盛り上がったことがありますが、そこで語られるのは名作ではなく、心に傷を残すような駄作ばかり。それぞれの「トラウマ映画」を笑い話にすることで、不思議な連帯感が生まれるんです。
また、「あまりにもひどいから逆に見てほしい」という推薦の仕方もあります。いわゆる「B級映画鑑賞会」のような形で、あえてクオリティの低い作品を皆で観て楽しむという文化もあるくらいです。
失敗作を共有する経験は、意外にも豊かなコミュニケーションを生み出すのです。
良作の価値を再認識できる
ハズレ映画を観た後に良い映画に出会うと、その素晴らしさがより際立って感じられます。
かつて私は1週間で3本の駄作を立て続けに観てしまい、「もう映画なんて…」と思っていたところ、友人に勧められた1本の名作に出会いました。その時の感動は今でも忘れられません。駄作が続いた後だったからこそ、その映画の素晴らしさが何倍にも感じられたのです。
良い映画と悪い映画の対比があることで、映画作りの難しさや、優れた監督・脚本家・俳優たちの才能の貴重さを再認識できます。
「当たり前のように面白い映画」など存在しないのだと気づき、良作に対する感謝の気持ちが生まれるのも、ハズレ映画を経験したからこそ。
映画体験の豊かさは、良い作品だけでなく、様々な質の作品に触れることで深まっていくものなのかもしれません。
部分的な良さを見つける訓練になる
全体としては残念な作品でも、部分的に光る要素を見つける目を養うことができます。
例えば、ストーリーは平凡でも撮影技術が素晴らしい、脚本は弱いが俳優の演技が光っている、全体的には退屈だが音楽だけは秀逸、といった「救いどころ」を見つける力が鍛えられるのです。
私が観た中でも「なぜこんな脚本で映画化したのか」と思うような作品でも、一人だけ異様に演技が良い俳優がいたり、一場面だけ鳥肌が立つような映像美があったりすることがあります。
そういった「部分的な良さ」に目を向けることで、映画鑑賞がより多角的になり、一見つまらない作品からも何かを得られるようになります。
これは映画だけでなく、人生の様々な場面でも役立つスキルかもしれません。完璧ではない状況の中でも、光る部分を見つけ出す力は、豊かな人生を送るために大切なことだと思います。
「ハズレ映画」回避テクニックのまとめ
今回は映画好きの私が長年の経験から編み出した「ハズレ映画」回避テクニックについてご紹介しました。
良い映画との出会いは、私たちの時間を豊かにしてくれる一方で、期待外れの映画は貴重な時間を無駄にしてしまいがち。
でも、この記事を参考にしていただければ、ハズレを引く確率はぐっと下がるはずです。
改めて、映画選びで失敗しないためのポイントをおさらいしましょう。
- 映画祭の受賞作や批評家の高評価作品をチェック
- 監督や俳優だけでなく、脚本家や撮影監督などの裏方情報も重視
- 配給会社の特色を知り、自分好みの会社の作品を選ぶ
- VODサービス内の特集やキュレーションを活用
- 映画SNSで自分と趣味の近いユーザーをフォロー
そして、もしハズレ映画を引いてしまっても、それを単なる失敗で終わらせず、次への学びと捉えることで、映画鑑賞の幅と深さが広がっていくことでしょう。
「ハズレ映画」回避テクニックを実践して、皆さんの映画ライフがより充実したものになることを願っています。
さあ、今夜はどんな映画を観ますか?
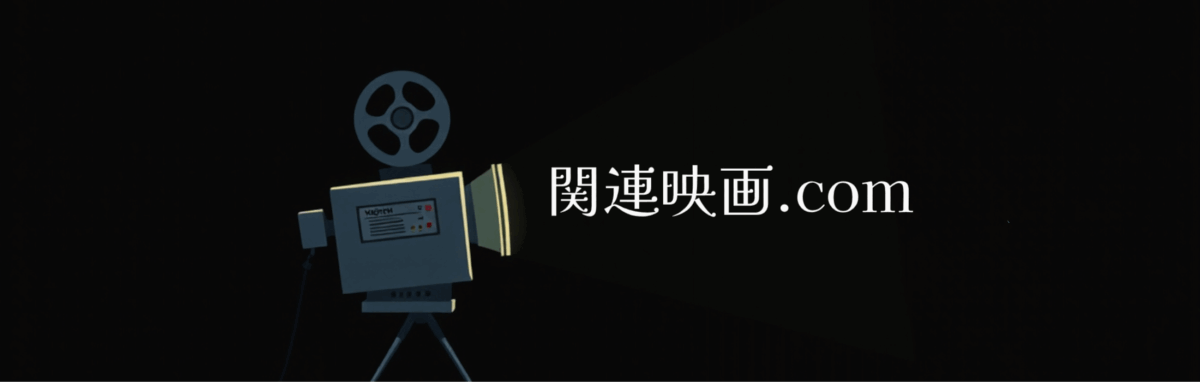

コメント